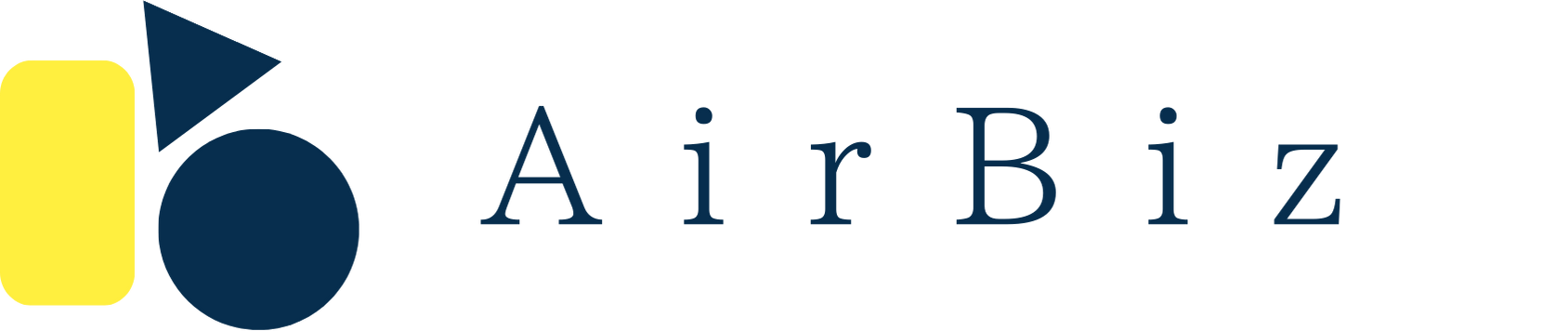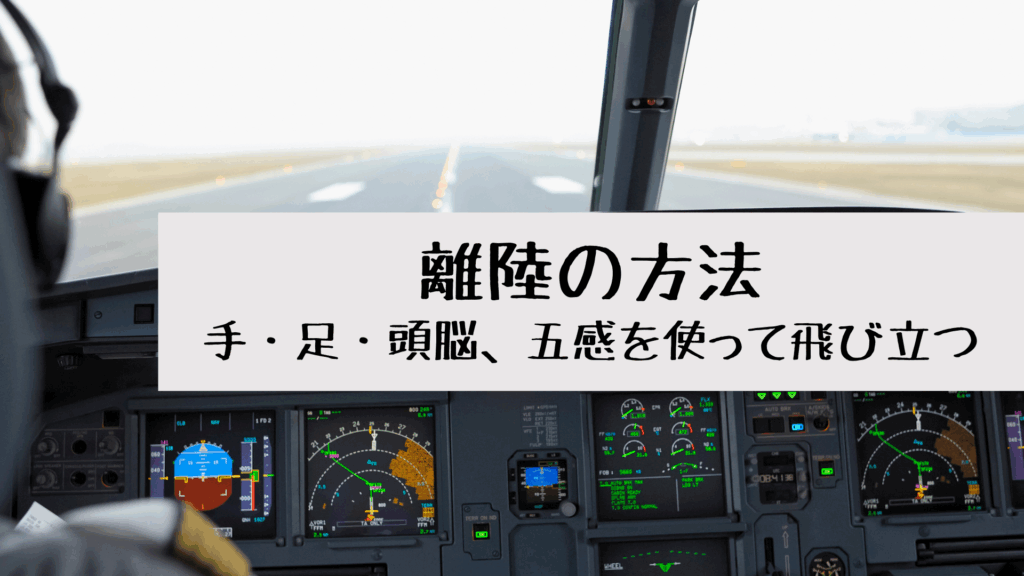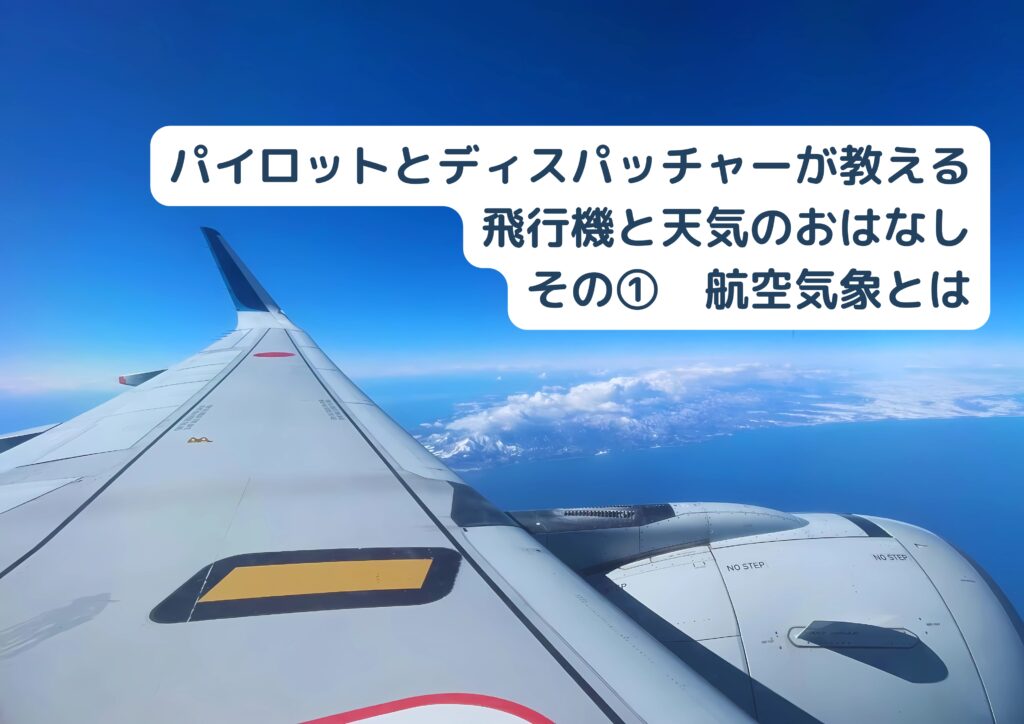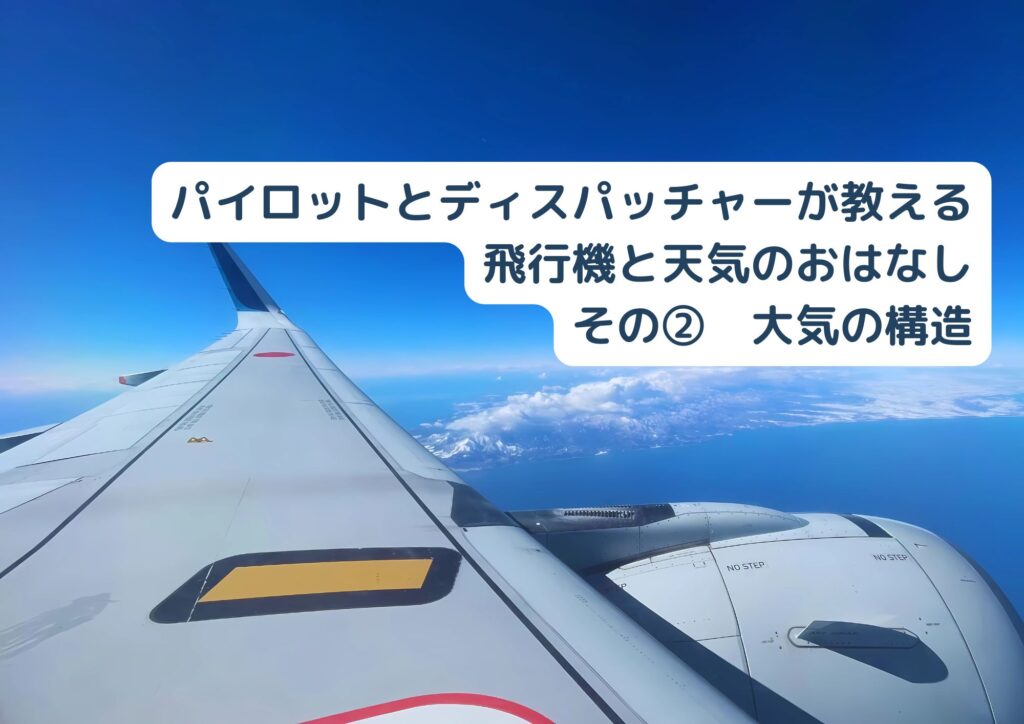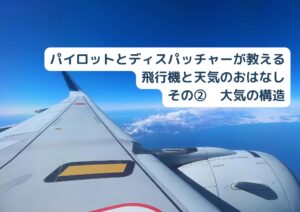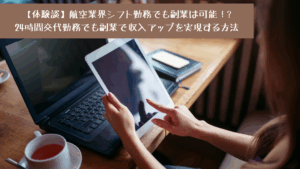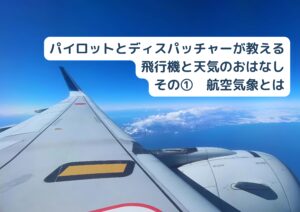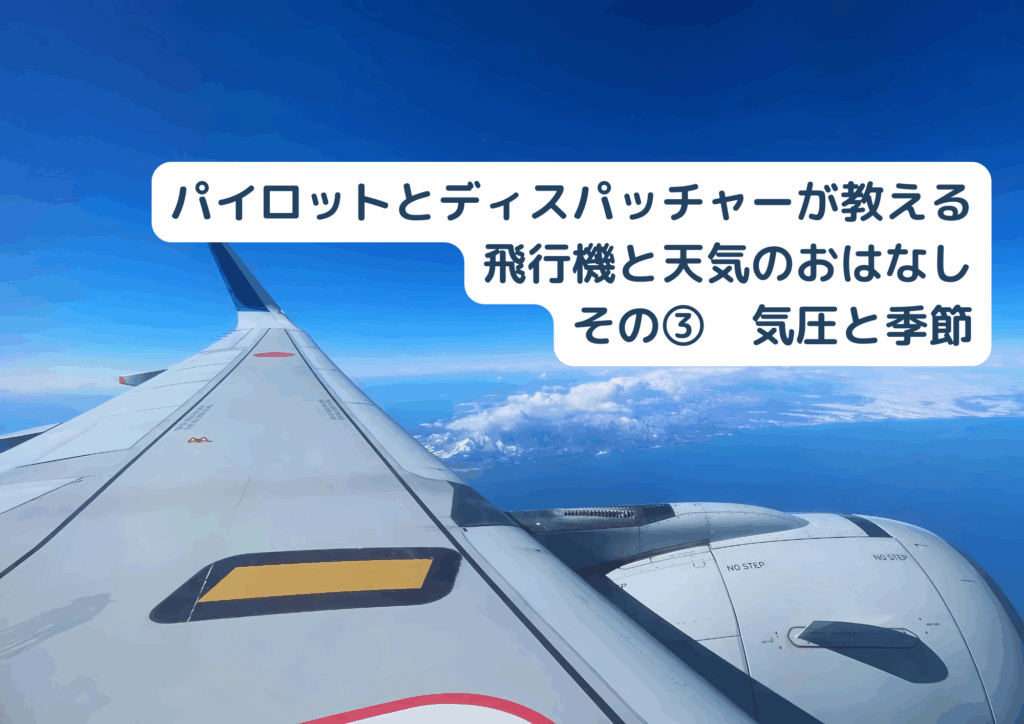
みなさんは毎日どんな空を見ていますか?
晴れの日もあれば、雨の日もあります。空の天気はいつも変わっていて、まるで生きているようです。
運航管理者は、常に最新の天気を把握し、適切な判断を行っています。
今回は天気図でおなじみの高気圧、低気圧、前線といった気象現象の基本的なメカニズムと、それらが日本の四季にどう影響しているかについて紹介します。
by Y.M
高気圧とは? 晴天をもたらす空気の塊
高気圧とは 周囲より気圧が高い領域のことです。中心から空気が吹き出し、北半球では時計回りに、南半球では反時計回りに循環します。上空から空気が下降するため、雲ができにくく、晴天をもたらします。
高気圧には様々な種類があります。
①冬の王様、寒冷高気圧
寒冷高気圧といわれる下層の気温が低い高気圧は、シベリア高気圧などが代表例です。
冬に発達し、日本海側に雪を降らせ、太平洋側に乾燥した晴天をもたらします。
②夏の王様、温暖高気圧
太平洋高気圧(小笠原高気圧)が代表例で、夏の安定した晴天をもたらします。
③移動性高気圧
偏西風に乗って移動する高気圧です。
春や秋によく見られ、この高気圧の影響で周期的に天気が変わります。
低気圧とは? 雨や雪をもたらす空気の塊
低気圧とは周囲より気圧が低い領域のことです。中心に向かって空気が流れ込み、北半球では反時計回りに、南半球では時計回りに循環します。空気が上昇するため雲ができやすく、雨や雪などの降水現象を伴います。
低気圧にも様々な種類があります。
①温帯低気圧
温帯低気圧は中緯度地域で見られる低気圧です。前線を伴い、発達すると暴風雨になることもあり、日本の天気に大きな影響を与えます。
②熱帯低気圧
熱帯低気圧は熱帯海上で発生する低気圧です。発達すると台風となり、強風や大雨による災害をもたらします。
前線とは?性質の違う空気のぶつかり合い
前線は、冷たい空気と暖かい空気がぶつかり合う境界線のことです。仲が悪い2つの空気がケンカするみたいに、雲がモクモクとできます。
梅雨の時期も前線が関係しています。日本の梅雨の時期には、「梅雨前線」という前線がずっと停滞して、雨の日が続きます。
日本の四季
日本には春夏秋冬の四季があります。これは、高気圧や低気圧、前線が季節によって変わるからです。
春はどんな天気?
移動性高気圧と低気圧が交互に通過し、天気が周期的に変化します。6月に入ると梅雨もはじまります。
夏はどんな天気?
太平洋高気圧に覆われ、安定した晴天が続きます。
台風の影響を受けることもあります。
秋はどんな天気?
秋雨前線や台風の影響で雨が多くなります。
移動性高気圧に覆われて晴れる日もあります。
冬はどんな天気?
シベリア高気圧が発達します。西高東低の気圧配置となり、日本海側で雪、太平洋側で晴れとなることが多いです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
以上のように高気圧、低気圧、前線は、それぞれ異なる性質を持ち、相互に影響し合いながら、様々な気象現象を引き起こします。
運航管理者はこれらの現象を理解することで、出発地、目的地、飛行経路上の天気予報をより深く理解し、適切な飛行経路、高度、燃料搭載量などを選定しています。また、悪天候により、安全な運航が困難と判断された場合は遅延や欠航の判断を行います。


次回も、どうぞお楽しみに!
※この記事の内容は、航空従事者の知見をもとに一般の方向けにわかりやすく構成したものです。実際の運航判断は、厳密な気象データと航空法に基づいて行われます。
みなさんは毎日どんな空を見ていますか?
晴れの日もあれば、雨の日もあります。空の天気はいつも変わっていて、まるで生きているようです。
運航管理者は、常に最新の天気を把握し、適切な判断を行っています。
今回は天気図でおなじみの高気圧、低気圧、前線といった気象現象の基本的なメカニズムと、それらが日本の四季にどう影響しているかについて紹介します。
私たちが「空」と呼んでいるもの、その中を飛行機がビュン!と飛んでいく様子を見ると、「空ってどこまで続いてるんだろう?」と思ったことはありませんか?
高気圧とは? 晴天をもたらす空気の塊
高気圧とは 周囲より気圧が高い領域のことです。
中心から空気が吹き出し、北半球では時計回りに、南半球では反時計回りに循環します。
上空から空気が下降するため、雲ができにくく、晴天をもたらします。
高気圧には様々な種類があります。
①冬の王様、寒冷高気圧
寒冷高気圧といわれる下層の気温が低い高気圧は、シベリア高気圧などが代表例です。
冬に発達し、日本海側に雪を降らせ、太平洋側に乾燥した晴天をもたらします。
②夏の王様、温暖高気圧
太平洋高気圧(小笠原高気圧)が代表例で、夏の安定した晴天をもたらします。
③移動性高気圧
偏西風に乗って移動する高気圧です。
春や秋によく見られ、この高気圧の影響で周期的に天気が変わります。
低気圧とは? 雨や雪をもたらす空気の塊
低気圧とは周囲より気圧が低い領域のことです。中心に向かって空気が流れ込み、北半球では反時計回りに、南半球では時計回りに循環します。空気が上昇するため雲ができやすく、雨や雪などの降水現象を伴います。
低気圧にも様々な種類があります。
①温帯低気圧
温帯低気圧は中緯度地域で見られる低気圧です。
前線を伴い、発達すると暴風雨になることもあり、日本の天気に大きな影響を与えます。
②熱帯低気圧
熱帯低気圧は熱帯海上で発生する低気圧です。
発達すると台風となり、強風や大雨による災害をもたらします。
前線とは?性質の違う空気のぶつかり合い
前線は、冷たい空気と暖かい空気がぶつかり合う境界線のことです。
仲が悪い2つの空気がケンカするみたいに、雲がモクモクとできます。
梅雨の時期も前線が関係しています。
日本の梅雨の時期には、「梅雨前線」という前線がずっと停滞して、雨の日が続きます。
日本の四季
日本には春夏秋冬の四季があります。これは、高気圧や低気圧、前線が季節によって変わるからです。
春はどんな天気?
移動性高気圧と低気圧が交互に通過し、天気が周期的に変化します。
6月に入ると梅雨もはじまります。
夏はどんな天気?
太平洋高気圧に覆われ、安定した晴天が続きます。
台風の影響を受けることもあります。
秋はどんな天気?
秋雨前線や台風の影響で雨が多くなります。
移動性高気圧に覆われて晴れる日もあります。
冬はどんな天気?
シベリア高気圧が発達します。西高東低の気圧配置となり、日本海側で雪、太平洋側で晴れとなることが多いです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
以上のように高気圧、低気圧、前線は、それぞれ異なる性質を持ち、相互に影響し合いながら、様々な気象現象を引き起こします。
運航管理者はこれらの現象を理解することで、出発地、目的地、飛行経路上の天気予報をより深く理解し、
適切な飛行経路、高度、燃料搭載量などを選定しています。
また、悪天候により、安全な運航が困難と判断された場合は遅延や欠航の判断を行います。


次回も、どうぞお楽しみに!
※この記事の内容は、航空従事者の知見をもとに一般の方向けにわかりやすく構成したものです。実際の運航判断は、厳密な気象データと航空法に基づいて行われますしたものです。実際の運航判断は、厳密な気象データと航空法に基づいて行われます
MOST READ
RECOMMEND