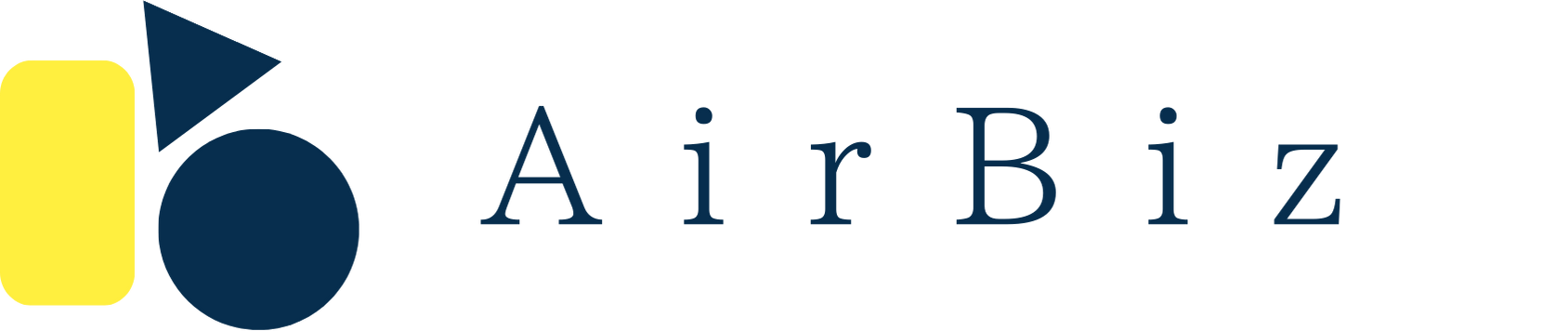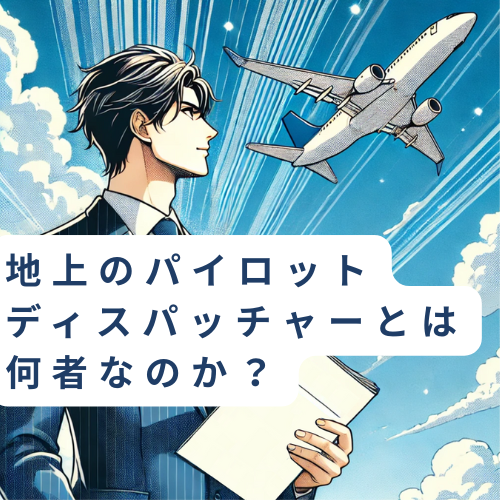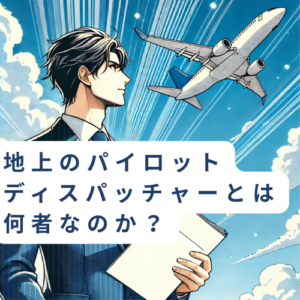前回の連載では、航空機の安全を地上から支える「運航管理者」という仕事の奥深さと魅力についてご紹介しました。
燃料計画を立て、飛行中の機体を見守り、時には緊急対応にも関わる。
その判断一つが、何百人、何千人という命に関わる――そんな責任とやりがいの詰まった仕事です。
「そんな仕事に、自分もいつか就いてみたい!」
そう思ってくださった方に、今回お届けするのがこのテーマです。
「運航管理者になるには?」
この仕事は誰でもすぐに就けるわけではなく、国家資格を必要とする専門職。
しかし、道は決して一つではありません。
文系・理系に関係なく、努力次第で誰にでもチャンスが開かれています。
それでは、実際にどのようなステップを踏めば、運航管理者という空のプロフェッショナルになれるのでしょうか?
わかりやすく、丁寧に解説していきます。
TEXT BY E.I
運航管理者になるための資格
運航管理者になるには、「運航管理者技能検定」という国家試験に合格しなければなりません。
この試験は国土交通省が定めた資格で、航空機の安全な運航を地上から管理するための専門知識と技能が問われます。
試験内容はかなり専門的で、出題範囲は以下の通り:
- 航空気象
- 航法(飛行ルートや測位の知識)
- 航空工学・航空力学(飛行機がどう飛ぶかを理解)
- 航空法規(航空法や関連する規制)
- 航空交通管制の知識
- 運航管理に必要なその他の知識
パッと見ただけでも、「難しそう…」と感じるかもしれません。
特に「理系じゃないと無理なのでは?」と感じる方もいると思います。
でも、実際には文系出身の運航管理者もたくさん活躍しているのです。
なぜなら、この試験で問われるのは単なる計算力や公式暗記ではなく、“状況を整理し、判断する力”。
つまり、運航管理者として必要なのは、「思考力」と「情報の扱い方」。これは理系・文系関係なく磨くことができるスキルです。また多くの運航管理者は、学生時代に勉強していた人は少なく、航空会社に入って初めて資格に挑戦する人がほとんどです。そのため、同時期に受験中の仲間の支え合いや運航管理者の先輩に教わりながら取得していく資格なのです。
試験を受けるためには「実務経験」が必要
運航管理者技能検定は、誰でもすぐに受験できるわけではありません。
この試験には、受験資格が定められています。
具体的には、試験を受けるには、国が定めた6つの分野のいずれかに関する経験が必要で、それぞれに最低年数の条件があります。
以下が、その6つの分野です:
- 操縦の経験
- 空中航法の経験
- 気象業務の経験
- 航空機に乗って無線機器を操作した経験
- 航空交通管制の経験
- 運航管理の補助業務の経験
これらのうち、「1~5」の経験は2年以上必要で、「6」の運航管理補助業務に関しては1年以上の経験が必要です。
つまり、最も早く運航管理者への道を進みたい場合は、航空会社などに就職して、運航管理の補助業務に就くことが現実的なルートということになります。
最短ルートは「航空会社に入社」して現場で学ぶこと
【ステップ1】 航空会社や地上支援会社に就職
新卒でも中途でも、航空会社や関連会社に就職して、運航管理の補助業務に関わる部署へ。
ここでは、ベテランの運航管理者の隣や空港で働きながら、業務の流れや判断の基準などを、実務を通じてリアルに学ぶことができます。
【ステップ2】 実務経験を積む(1年以上)
1年以上の補助業務の経験を積むことで、国家試験の受験資格が得られます。
この期間が、まさに「運航管理者のたまご」として育つフェーズ。
現場でのやりとり、突発的な事象への対応など、日々が学びの連続です。
【ステップ3】 国家試験にチャレンジ
受験資格を得たら、いよいよ本格的な勉強に取り組み、国家試験にチャレンジ。
過去問や専門テキストを使って知識を固め、航空会社が用意する教育や模擬試験などのサポートも受けられる場合もあります。
【ステップ4】 航空会社の社内試験に合格
国家試験に合格しても、最後は所属する航空会社が定めた社内試験やチェックをパスしなければ、正式に「運航管理者」として業務に従事することはできません。
運航は安全第一。だからこそ、どの会社も「この人に任せられる」と判断するまでは、しっかりと訓練を積ませます。
受験は、「ひとりじゃない」
ここまで読んで、「やっぱり難しそう…」と思った方もいるかもしれません。
でも、知っておいてほしいのは──
「運航管理者を目指す道は、決して孤独じゃない」ということ。
実は、運航管理者試験の受験者は、同じ航空会社の中で同期として目指している仲間がいたり、
先輩運航管理者が丁寧に教えてくれたりする文化があります。
たとえば…
試験前に社内で勉強会が開かれる
自主的に集まって問題を出し合うグループがある
わからないところを、経験豊富な先輩に聞ける
直前期には模試や予想問題をシェアし合う
…といった環境があるんです。
だから、試験に挑むときも「みんなで乗り越えよう」という雰囲気があり、チームで運航を支える文化が、受験勉強の時点から根付いていると言っても過言ではありません。
実際に私も、周囲に助けられながら技能検定に合格することができました。こうした資格取得にもチームで取り組むのは航空会社ならではの文化なのかもしれません。
文系でも、未経験でも、空はあなたを待っている
理系出身でなくても、パイロットのような経験がなくても、空を支えたいという強い気持ちがあれば、運航管理者を目指すことはできます。
文系出身で活躍している運航管理者は少なくありませんし、むしろ多いかと思います。
逆に、言語能力や情報整理力、コミュニケーション力に長けた文系人材だからこそ、
「チームでの判断」「お客様視点の調整」「管制とのやり取り」などで実力を発揮する場面も多いのです。
空を支える仕事、それが運航管理者。ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
前回の連載では、航空機の安全を地上から支える「運航管理者」という仕事の奥深さと魅力についてご紹介しました。
燃料計画を立て、飛行中の機体を見守り、時には緊急対応にも関わる。
その判断一つが、何百人、何千人という命に関わる――そんな責任とやりがいの詰まった仕事です。
「そんな仕事に、自分もいつか就いてみたい!」
そう思ってくださった方に、今回お届けするのがこのテーマです。
「運航管理者になるには?」
この仕事は誰でもすぐに就けるわけではなく、国家資格を必要とする専門職。
しかし、道は決して一つではありません。
文系・理系に関係なく、努力次第で誰にでもチャンスが開かれています。
それでは、実際にどのようなステップを踏めば、運航管理者という空のプロフェッショナルになれるのでしょうか?
わかりやすく、丁寧に解説していきます。
TEXT BY E.I
運航管理者になるための資格
運航管理者になるには、「運航管理者技能検定」という国家試験に合格しなければなりません。
この試験は国土交通省が定めた資格で、航空機の安全な運航を地上から管理するための専門知識と技能が問われます。
試験内容はかなり専門的で、出題範囲は以下の通り:
- 航空気象
- 航法(飛行ルートや測位の知識)
- 航空工学・航空力学(飛行機がどう飛ぶかを理解)
- 航空法規(航空法や関連する規制)
- 航空交通管制の知識
- 運航管理に必要なその他の知識
パッと見ただけでも、「難しそう…」と感じるかもしれません。
特に「理系じゃないと無理なのでは?」と感じる方もいると思います。
でも、実際には文系出身の運航管理者もたくさん活躍しているのです。
なぜなら、この試験で問われるのは単なる計算力や公式暗記ではなく、“状況を整理し、判断する力”。
つまり、運航管理者として必要なのは、「思考力」と「情報の扱い方」。これは理系・文系関係なく磨くことができるスキルです。また多くの運航管理者は、学生時代に勉強していた人は少なく、航空会社に入って初めて資格に挑戦する人がほとんどです。そのため、同時期に受験中の仲間の支え合いや運航管理者の先輩に教わりながら取得していく資格なのです。
試験を受けるためには「実務経験」が必要
運航管理者技能検定は、誰でもすぐに受験できるわけではありません。
この試験には、受験資格が定められています。
具体的には、試験を受けるには、国が定めた6つの分野のいずれかに関する経験が必要で、それぞれに最低年数の条件があります。
以下が、その6つの分野です:
- 操縦の経験
- 空中航法の経験
- 気象業務の経験
- 航空機に乗って無線機器を操作した経験
- 航空交通管制の経験
- 運航管理の補助業務の経験
これらのうち、「1~5」の経験は2年以上必要で、「6」の運航管理補助業務に関しては1年以上の経験が必要です。
つまり、最も早く運航管理者への道を進みたい場合は、航空会社などに就職して、運航管理の補助業務に就くことが現実的なルートということになります。
最短ルートは「航空会社に入社」して現場で学ぶこと
【ステップ1】 航空会社や地上支援会社に就職
新卒でも中途でも、航空会社や関連会社に就職して、運航管理の補助業務に関わる部署へ。
ここでは、ベテランの運航管理者の隣や空港で働きながら、業務の流れや判断の基準などを、実務を通じてリアルに学ぶことができます。
【ステップ2】 実務経験を積む(1年以上)
1年以上の補助業務の経験を積むことで、国家試験の受験資格が得られます。
この期間が、まさに「運航管理者のたまご」として育つフェーズ。
現場でのやりとり、突発的な事象への対応など、日々が学びの連続です。
【ステップ3】 国家試験にチャレンジ
受験資格を得たら、いよいよ本格的な勉強に取り組み、国家試験にチャレンジ。
過去問や専門テキストを使って知識を固め、航空会社が用意する教育や模擬試験などのサポートも受けられる場合もあります。
【ステップ4】 航空会社の社内試験に合格
国家試験に合格しても、最後は所属する航空会社が定めた社内試験やチェックをパスしなければ、正式に「運航管理者」として業務に従事することはできません。
運航は安全第一。だからこそ、どの会社も「この人に任せられる」と判断するまでは、しっかりと訓練を積ませます。
受験は、「ひとりじゃない」
ここまで読んで、「やっぱり難しそう…」と思った方もいるかもしれません。
でも、知っておいてほしいのは──
「運航管理者を目指す道は、決して孤独じゃない」ということ。
実は、運航管理者試験の受験者は、同じ航空会社の中で同期として目指している仲間がいたり、先輩運航管理者が丁寧に教えてくれたりする文化があります。
たとえば…
試験前に社内で勉強会が開かれる
自主的に集まって問題を出し合うグループがある
わからないところを、経験豊富な先輩に聞ける
直前期には模試や予想問題をシェアし合う
…といった環境があるんです。
だから、試験に挑むときも「みんなで乗り越えよう」という雰囲気があり、チームで運航を支える文化が、受験勉強の時点から根付いていると言っても過言ではありません。
実際に私も、周囲に助けられながら技能検定に合格することができました。こうした資格取得にもチームで取り組むのは航空会社ならではの文化なのかもしれません。
文系でも、未経験でも、空はあなたを待っている
理系出身でなくても、パイロットのような経験がなくても、空を支えたいという強い気持ちがあれば、運航管理者を目指すことはできます。
文系出身で活躍している運航管理者は少なくありませんし、むしろ多いかと思います。
逆に、言語能力や情報整理力、コミュニケーション力に長けた文系人材だからこそ、「チームでの判断」「お客様視点の調整」「管制とのやり取り」などで実力を発揮する場面も多いのです。
空を支える仕事、それが運航管理者。ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
MOST READ